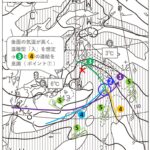はじめに
豆知識24と34で簡単に述べたとおり、温帯低気圧が発達する過程で、寒冷前線が温暖前線に追いついたとき、その2つの前線が重なり合う部分を閉塞前線と呼びます。
そのときはお話しませんでしたが、閉塞前線は、寒冷型閉塞前線と温暖型閉塞前線に分けられます。今回の豆知識では、両者の特徴を図解します。
地上天気図からみた寒冷型閉塞前線と温暖型閉塞前線
まずは、寒冷型閉塞前線。図1をご覧ください。この図には、地上実況天気図に描かれた寒冷型閉塞前線の4つの事例を示しました。
これらの事例で分かるように、寒冷型閉塞前線は、寒冷前線の延長上に形成されます(図中の赤の矢印)。このため、「寒冷型閉塞前線、寒冷前線、温暖前線」を1つのまとまりとした場合、漢字の「人」の字のように見えます。

図1 地上実況天気図に描かれた寒冷型閉塞前線の4つの事例(気象庁提供の天気図を一部拡大)
注)①は2022年1月12日9時、②は2022年11月10日15時、③は2023年4月21日9時、④は2023年4月27日18時の速報天気図。注目する寒冷型閉塞前線に、赤の矢印を記入した。
次に、温暖型閉塞前線。図2をご覧ください。この図には、温暖型閉塞前線の4つの事例を示しました。
これらの事例で分かるように、温暖型閉塞前線は、温暖前線の延長上に形成されます(図中の赤の矢印)。このため、「温暖型閉塞前線、温暖前線、寒冷前線」を1つのまとまりとした場合、漢字の「入」の字のように見えます。

図2 地上実況天気図に描かれた温暖型閉塞前線の4つの事例(気象庁提供の天気図を一部拡大)
注)①は2021年11月8日6時、②は2022年4月5日15時、③は2022年11月16日15時、④は2023年1月24日6時の速報天気図。注目する温暖型閉塞前線に、赤の矢印を記入した。
寒冷型閉塞前線と温暖型閉塞前線の形成過程と構造
豆知識19で述べたとおり、暖気と寒気のように、2つの性質の異なる空気がぶつかりあうことによって、前線が発生します。ただし、寒気と寒気のぶつかりあいであっても、気温差など両者の空気に性質の違いがあれば、前線は発生します。
まず、寒冷型閉塞前線が形成される過程をみていきます。図3(左)をご覧ください。この図は、低気圧が北側にあると仮定して、南側(横)からみた東西鉛直断面図です。
①において、Aは寒冷前線の西側の寒気団、Bは温暖前線の東側の寒気団、Cは暖気団とします。低気圧(前線)が東に進む場合、進行方向後面の寒気団Aの方が、前面の寒気団Bより気温が低い場合(①)、寒気団Aは寒気団Bを持ち上げてその下に突入し、寒気団Bと暖気団Cを上空に持ち上げます(②~③)。すなわち、低気圧の中心付近で地上から暖気団は姿を消し、低気圧は閉塞します。
この状態を、上から見た図が、図4(左)の下段の図です。このような構造を持つ、赤色で示した閉塞前線を、寒冷型閉塞前線と呼びます。

図3 寒冷型閉塞前線(左)と温暖型閉塞前線(右)の形成過程(東西鉛直断面図)
注)気団A、B、Cに記入した気温は、それぞれの気団の相対的な温度差を分かりやすく表現するための架空の値。

図4 寒冷型閉塞前線(左)と温暖型閉塞前線(右)の模式図
注)左右の図ともに、上段は閉塞前線を通る東西鉛直断断面図(南側から見た図)。下段は、上から見た図。上段の図を囲んだ緑色の線と、下段の緑色の一本線が対応する。
次に、温暖型閉塞前線が形成される過程をみていきます。図3(右)をご覧ください。低気圧進行方向後面の寒気団Aの方が、前面の寒気団Bより気温が高い場合(①)、寒気団Aは寒気団Bの上を這いあがりながら進み、暖気団Cを上空に持ち上げます(②~③)。すなわち、地上から暖気団は姿を消し、低気圧は閉塞します。この状態を、上から見た図が、図4(右)の下段の図です。このような構造を持つ、赤色で示した閉塞前線を、温暖型閉塞前線と呼びます。
寒冷型閉塞前線の後面と前面の気温差(7事例)
既に述べたとおり、寒冷型閉塞前線の特徴として、進行方向後面にある寒気の方が、進行方向前面にある寒気より強いことがあげられます。その具体例をみてみましょう。図5①は、2024年5月22日21時の地上実況天気図です。注目する低気圧の中心に赤の×印、そこからのびる閉塞前線に赤の矢印を記入しました。
図5②は、同時刻の850hPa 気温・風 予想図です。①の低気圧の中心(赤の×印)と同じ場所に、②では黄色の×印を記入。また、①の閉塞前線と同じ場所に、②では黄色の実線を記入しました。
閉塞前線(黄色の実線)の進行方向後面と、前面の気温を比べてみます。閉塞前線の後面には相対的に冷たい空気が流入し、矢印で示した任意地点の気温は-1℃。一方、閉塞前線の前面には相対的に暖かい空気が流入し、矢印で示した任意地点の気温は3℃。これらはあくまでも任意の地点の気温であり、地点によって差はあるものの、全体的に後面の気温の方がやや低い傾向が見られました。

図5 2024年5月22日21時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)①は気象庁提供の天気図を一部拡大。②は欧州中期予報センターの数値予報モデルによる予測値(Windy.comのwebサイトより入手)。
①:注目する低気圧の中心に、赤の×印を記入。そこからのびる閉塞前線に赤の矢印を記入。
②:実線は等温線。気温の分布は、色を変えて表示。細く途切れた線は、風の流れを示す(実際のweb上では粒子アニメーションで表示)。①の低気圧の中心(赤の×印)と同じ場所に、②では黄色の×印を記入。また、①の閉塞前線と同じ場所に、②では黄色の実線を記入。閉塞前線の進行方向前面、および後面の任意の1地点について、等温線から気温を読み取り、その値を記入した。
さらに、別の日時の6つの事例も紹介します(図6~11)。これらの日時の寒冷型閉塞前線についても、全体的に閉塞前線後面の気温の方が、前面の気温よりもやや低い。つまり、進行方向後面にある寒気の方が、前面にある寒気より強い傾向がみられました。

図6 2024年5月2日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。

図7 2024年7月2日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。

図8 2024年9月21日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。

図9 2024年12月26日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。

図10 2025年4月30日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。

図11 2024年10月24日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。
温暖型閉塞前線の後面と前面の気温差(6事例)
既に述べたとおり、温暖型閉塞前線の特徴として、進行方向後面にある寒気の方が、進行方向前面にある寒気より弱いことがあげられます。その具体例をみてみましょう。図12①は2025年3月6日21時の地上実況天気図、図12②は同時刻の850hPa 気温・風 予想図です。図中の注釈は、図5の場合と同じです。
温暖型閉塞前線(黄色の実線)の進行方向後面と、前面の気温を比べてみます。矢印で示した後面の任意地点の気温は7℃、前面の任意地点の気温は3℃。これらはあくまでも任意の地点の気温であり、地点によって差はあるものの、全体的に後面の気温の方がやや高い傾向が見られました。

図12 2025年3月6日21時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。
さらに、別の日時の5つの事例も紹介します(図13~17)。これらの日時の温暖型閉塞前線についても、全体的に閉塞前線後面の気温の方が、前面の気温よりもやや高い。つまり、進行方向後面にある寒気の方が、前面にある寒気より弱い傾向がみられました。

図13 2024年5月28日21時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。

図14 2024年5月30日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。

図15 2024年6月22日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。

図16 2024年6月30日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。

図17 2025年3月17日9時の地上実況天気図(①)及び850hPa 気温・風 予想図(②)
注)注釈については、図5を参照。
さいごに
今回は、地上天気図からみた寒冷型閉塞前線と温暖型閉塞前線の違いを紹介しました。さらに、両者はどのようにして形成されるのか、図を用いてお話しました。
寒冷型閉塞前線については、進行方向の後面の寒気が、前面の寒気の下に潜り込むようにしながら進むので(図3左、図4左)、寒冷前線の構造に似ています。一方、温暖型閉塞前線については、進行方向の後面の寒気が、前面の寒気の上を這いあがりながら進むので(図3右、図4右)、温暖前線の構造に似ています。
次回の豆知識では、閉塞前線を地上天気図に引くときのポイントについて、気象予報士試験の問題を交えながら、お話する予定です。
今回の豆知識で参考にした図書等
●浅井冨雄,内田英治,河村 武 監修(1999)増補 気象の事典,平凡社
●安斎政雄(1998) 新・天気予報の手引(改訂29版),日本気象協会
●岩槻秀明(2017) 気象学のキホンがよ~くわかる本(第3版),秀和システム
●気象庁のwebサイト
●中島俊夫(2022)イラスト図解 よくわかる気象学 実技編,ナツメ社
●Windy.comのwebサイト