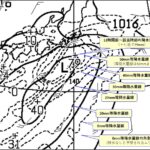はじめに
豆知識3で述べたとおり、温帯では、熱帯や寒帯と比べ南北方向の気温傾度(気圧傾度)が大きく、西風が強くなります。また、上空ほど等圧面の傾きが大きいため、それに対応して上空ほど風は強くなります。
その強い西風(偏西風)の中でも、特に風速の大きい細い流れをジェット気流と呼びます。ジェット気流は、その気温差によってできる強い流れですので、ジェット気流に着目して、低気圧の発達を知ることもできます。そこで、今回は、低気圧の発達過程において、ジェット気流(強風軸)と地上の低気圧の位置関係がどのように変化するのか、お話します。
ジェット気流(強風軸)と地上低気圧の位置関係
ジェット気流と強風軸について
ジェット気流は圏界面(対流圏と成層圏の境目)付近の上空9000~12000m付近に出現し、空間的には、長さ数千km、幅数百km、厚さは数kmの広がりを持っています。その最大風速は、50~100m/sに達することもあります。
300hPa面(約9000m)や500hPa面(約5500m)の高層天気図においてジェット気流を解析する場合、風速の最も大きい流れに注目します。この場合、高層天気図上の強風域は、圏界面付近のジェット気流の軸を取り巻く風速の大きい領域が、下方にのびた部分に相当します(図1)。

図1 ジェット気流のイメージ図
注)南北鉛直断面図を横切る東西風を、横(西側)から見た断面図。赤色が濃いほど西風が強いこと、Jはジェット気流を表す。
高層天気図におけるジェット気流の解析では、強風軸が重要な手がかりとなります。強風軸とは、高層天気図上での強風帯の中心を結んだ線のことです。
豆知識10で述べたとおり、500hPa 高度・渦度解析図において、北極側に正渦度域、赤道側に負渦度域がある場合、正渦度と負渦度の境目(渦度0線)が強風軸と対応します(図2)。

図2 渦度0線と強風軸(豆知識10の図10に、一部加筆し再掲載)
閉塞前線について
図3をご覧ください。温帯低気圧の発達過程において、低気圧の中心からのびる寒冷前線は、一般に温暖前線より移動が速く、ついには温暖前線に追いつきます。
その重なった部分は閉塞前線と呼ばれます(図3②の赤枠で囲んだ部分)。閉塞前線が形成され始めると、低気圧は閉塞期に向かいます。閉塞前線と温暖前線・寒冷前線が交わっている部分は、閉塞点と呼ばれます(図3②の青の×印)。

図3 地上天気図に描かれた低気圧の発達過程(気象庁提供の天気図の一部を拡大)
注)①は2023年5月15日21時、②は2023年5月17日3時。注目する低気圧の中心位置を赤の×印、閉塞点を青の×印、閉塞前線を赤の実線で囲んだ。
ジェット気流と低気圧の位置関係
図4は、温帯低気圧の発生・発達過程におけるジェット気流(強風軸)、上空の気圧の谷(トラフ)、および地上の低気圧の位置関係を模式的に表したものです。トラフと低気圧の位置関係については、豆知識9を参照してください。今回は、ジェット気流と低気圧の位置関係に注目します。
低気圧の発生期は、地上の低気圧とジェット気流は離れています(図4①)。つまり、低気圧はジェット気流の南側に位置しています。
低気圧は、発達しながら、ジェット気流の南側に接近してきます(図4②)。つまり、発達期の低気圧は、ジェット気流のすぐ南側、あるいは真下付近に位置しています。
低気圧の最盛期(閉塞期)には、その中心(赤の×印)はジェット気流の北側に移ります。ここで、閉塞点(青の×)とジェット気流との関係をみると、閉塞点の真上付近にジェット気流が位置していることが分かります(図4③)。

図4 ジェット気流(強風軸)、上空の気圧の谷(トラフ)、および地上の低気圧の位置関係
強風軸と低気圧の位置関係に注目した事例
低気圧の発達(閉塞)過程において、500hPaの強風軸と地上の低気圧の位置関係に注目した事例を、気象予報士試験問題を交えて3つ紹介します。
2015年2月26~27日の事例
2015年2月26日~27日に発達した低気圧
図5~8 は、2015年2月26日9時~27日21時の地上天気図です。2月26日9時に九州南岸付近にあった低気圧は、その後、発達しながら北東に進みました。

図5 2015年2月26日9時の地上天気図
注)気象庁提供の地上実況天気図(速報天気図)。注目する低気圧の中心位置を、赤の矢印で示した。

図6 2015年2月26日21時の地上天気図
注)注釈については、図5を参照。

図7 2015年2月27日9時の地上天気図
注)注釈については、図5を参照。

図8 2015年2月27日21時の地上天気図
注)注釈については、図5を参照。
第48回気象予報士試験実技1
上記の低気圧と500hPaの強風軸との位置関係に関する試験問題が、第48回実技1問2(3)③で出題されました。図9 ~15は、その試験問題からの抜粋です。

図9 第48回実技1問2(3)③

図10 500hPa高度・渦度12時間予想図(第48回実技1より引用)
注)太実線:高度(m), 破線および細実線:渦度(10-6 /s ), (網掛け域:渦度>0)
初期時刻 XX年2月26日9時(00UTC)

図11 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第48回実技1より引用)
注)実線:気圧(hPa), 破線:予想時刻前12時間降水量(mm)矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット,長矢羽:10ノット,旗矢羽:50ノット)
初期時刻 XX年2月26日9時(00UTC)

図12 500hPa高度・渦度24時間予想図(第48回実技1より引用)
注)注釈については、図10を参照。

図13 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第48回実技1より引用)
注)注釈については、図11を参照。

図14 500hPa高度・渦度36時間予想図(第48回実技1より引用)
注)注釈については、図10を参照。

図15 地上気圧・降水量・風 36時間予想図(第48回実技1より引用)
注)注釈については、図11を参照。
図16は、500hPaの12時間予想図(図10)に、解答を導くうえで注目する点を私が書き込んだものです。前述のとおり(図2)、北側の正渦度域(網掛け領域)と、南側の負渦度域(白い領域)の境目が強風軸(渦度0線)となります。このことに基づき、図16に、強風軸(渦度0線)を赤の矢印で記入しました。さらに、地上の12時間予想図(図11)から低気圧の中心位置を読み取り、図16の同じ場所に赤の×印を記入しました。試験問題は「低気圧と500hPaの強風軸との位置関係を20字程度で」とされているので、解答は「低気圧は強風軸から南側に離れている(18字、気象業務支援センター)」となります。

図16 解答を導くうえで注目した点(12時間予想図)
注)500hPaの12時間予想図(図10)に、強風軸(渦度0線)を赤の矢印で記入。さらに、地上の12時間予想図(図11)から読み取った低気圧の中心位置に、赤の×印を記入。
図17は、500hPaの24時間予想図(図12)に、注目点を書き込んだものです。つまり、北側の正渦度域と、南側の負渦度域の境目を強風軸(渦度0線)として、図17に赤の矢印を記入。さらに、地上の24時間予想図(図13)から低気圧の中心位置を読み取り、図17の同じ場所に赤の×印を記入しました。赤の矢印と×印の位置関係から、解答は「低気圧は強風軸のすぐ南側に位置している(20字、気象業務支援センター)」となります。

図17 解答を導くうえで注目した点(24時間予想図)
注)500hPaの24時間予想図(図12)に、強風軸(渦度0線)を赤の矢印で記入。さらに、地上の24時間予想図(図13)から読み取った低気圧の中心位置に、赤の×印を記入。
図18は、500hPaの36時間予想図(図14)に、注目点を書き込んだものです。つまり、強風軸(渦度0線)を、図18に赤の矢印で記入。さらに、地上の36時間予想図(図15)から低気圧の中心位置を読み取り、図18の同じ場所に赤の×印を記入しました。赤の矢印と×印の位置関係から、解答は「低気圧は強風軸の北側に位置している(18字、気象業務支援センター)」となります。

図18 解答を導くうえで注目する点(36時間予想図)
注)500hPaの36時間予想図(図14)に、強風軸(渦度0線)を赤の矢印で記入。さらに、地上の36時間予想図(図15)から読み取った低気圧の中心位置に、赤の×印を記入。
解答は、ここまでです。参考までに、この試験問題の対象時刻を、図5~8(2月26日9時~27日21時の地上天気図)と対応させてみましょう。
初期時刻は図5の時刻、12時間後(図16)は図6の時刻、24時間後(図17)は図7の時刻、36時間後(図18)は図8の時刻に、それぞれ対応しますね。
また、試験問題中の低気圧の発達段階を、図4①~③と対応させてみましょう。12時間後(図16)は図4①~②、24時間後(図17)は図4②、36時間後(図18)は図4③と、それぞれおおまかに対応していると言えます。
2019年11月17~18日の事例
2019年11月17日~18日に発達した低気圧
図19~21 は、2019年11月17日21時~18日21時の地上天気図です。11月17日21時に黄海付近にあった低気圧は、その後、発達しながら北東に進みました。

図19 2019年11月17日21時の地上天気図
注)注釈については、図5を参照。

図20 2019年11月18日9時の地上天気図
注)注釈については、図5を参照。

図21 2019年11月18日21時の地上天気図
注)注釈については、図5を参照。
第58回気象予報士試験実技2
上記の低気圧と500hPaの強風軸との位置関係に関する試験問題が、第58回実技2問2(1)②で出題されました。図22 ~27は、その試験問題からの抜粋です。

図22 第58回実技2問2(1)②

図23 地上天気図(第58回実技2より引用)
注)XX年11月17日21時(12UTC)実線・破線:気圧(hPa)矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット、長矢羽:10ノット、旗矢羽:50ノット)

図24 500hPa高度・渦度12時間予想図(第58回実技2より引用)
注)太実線:高度(m)、破線および細実線:渦度(10-6 /s )(網掛け域:渦度>0)
初期時刻 XX年11月17日21時(12UTC)

図25 地上気圧・降水量・風 12時間予想図(第58回実技2より引用)
注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット、長矢羽:10ノット、旗矢羽:50ノット)
初期時刻 XX年11月17日21時(12UTC)

図26 500hPa高度・渦度24時間予想図(第58回実技2より引用)
注)注釈については、図24を参照。

図27 地上気圧・降水量・風 24時間予想図(第58回実技2より引用)
注)注釈については、図25を参照。
図28は、500hPaの12時間予想図(図24)に、解答を導くうえで注目する点を、私が書き込んだものです。つまり、北側の正渦度域と、南側の負渦度域の境目を強風軸(渦度0線)として、図28に赤の矢印を記入。さらに、地上の12時間予想図(図25)から低気圧の中心位置を読み取り、図28の同じ場所に赤の×印を記入しました。
試験では「地上低気圧の中心位置の500hPaの強風軸に対する位置関係」が問われていますが、12時間後については、既に答えが問題文中に記載されています(図22)。つまり「ほぼ真下」と書かれており、実際にそのとおりですね(図28)。

図28 解答を導くうえで注目した点(12時間予想図)
注)500hPaの12時間予想図(図24)に、強風軸(渦度0線)を赤の矢印で記入。さらに、地上の12時間予想図(図25)から読み取った低気圧の中心位置に、赤の×印を記入。
図29は、500hPaの24時間予想図(図26)に、注目点を書き込んだものです。つまり、強風軸(渦度0線)を、図29に赤の矢印で記入。さらに、地上の24時間予想図(図27)から低気圧の中心位置を読み取り、図29の同じ場所に、赤の×印を記入しました。低気圧の中心位置(×印)の強風軸(矢印)に対する位置関係が問われているので、解答は「㋔高緯度側(気象業務支援センター)」となります。

図29 解答を導くうえで注目した点(24時間予想図)
注)500hPaの24時間予想図(図26)に、強風軸(渦度0線)を赤の矢印で記入。さらに、地上の24時間予想図(図27)から読み取った低気圧の中心位置に、赤の×印を記入。
解答は、ここまでです。参考までに、この試験問題の対象時刻を、図19~21(11月17日21時~18日21時の地上天気図)と対応させてみましょう。
初期時刻は図19の時刻、12時間後(図28)は図20の時刻、24時間後(図29)は図21の時刻に、それぞれ対応しますね。
また、試験問題中の低気圧の発達段階を、図4①~③と対応させてみましょう。12時間後(図28)は図4②、24時間後(図29)は図4③と、それぞれおおまかに対応していると言えます。
2020年4月18日の事例
2020年4月18日の低気圧
図30は、2020年4月18日21時の地上天気図です。福島県付近にある低気圧が西に進んでいます。

図30 2020年4月18日21時の地上天気図
注)注釈については、図5を参照。
第59回気象予報士試験実技1
上記の低気圧と500hPaの強風軸との位置関係に関する試験問題が、第59回実技1問2(4)で出題されました。図31~33は、その試験問題からの抜粋です。

図31 第59回実技1問2(4)

図32 500hPa高度・渦度36時間予想図(第59回実技1より引用)
注)太実線:高度(m)、破線および細実線:渦度(10-6 /s )(網掛け域:渦度>0)
初期時刻 XX年4月17日9時(00UTC)

図33 地上気圧・降水量・風 36時間予想図(第59回実技1より引用)
注)実線:気圧(hPa)、破線:予想時刻前12時間降水量(mm)矢羽:風向・風速(ノット)(短矢羽:5ノット、長矢羽:10ノット、旗矢羽:50ノット)
初期時刻 XX年4月17日9時(00UTC)
図34は、500hPaの36時間予想図(図32)に、解答を導くうえで注目する点を、私が書き込んだものです。つまり、北側の正渦度域と、南側の負渦度域の境目を強風軸(渦度0線)として、図34に赤の矢印を記入。さらに、地上の36時間予想図(図33)から低気圧の中心位置を読み取り、図34の同じ場所に赤の×印を記入しました。試験では「地上低気圧の中心は、500hPa面の渦度ゼロの等値線から推測される(①)の(②)に位置する」という文章中の、①と②が問われています。よって、解答は「①強風軸、②北側(気象業務支援センター)」となります。

図34 解答を導くうえで注目した点(36時間予想図)
注)500hPaの36時間予想図(図32)に、強風軸(渦度0線)を赤の矢印で記入。さらに、地上の36時間予想図(図33)から読み取った低気圧の中心位置に、赤の×印を記入。
解答は、ここまでです。参考までに、この試験問題の36時間後(図34)の対象時刻は、図30(4月18日21時の地上天気図)と対応しますね。また、試験問題中の低気圧の発達段階を、図4と対応させると、36時間後(図34)は図4③と、おおまかに対応していると言えます。
さいごに
今回は、低気圧の発達過程において、ジェット気流(強風軸)と地上の低気圧の位置関係が、どのように変化するのか、まずは模式図を使って考えてみました。さらに、具体的事例を、過去の気象予報士の試験問題の中から紹介しました。
これらの例のとおり、ジェット気流の存在は、地上の低気圧の発達に大いに関係しています。なお、低気圧の発達には「ジェット気流」以外にも、「上空の気圧の谷(トラフ)」「暖気移流と寒気移流」「上昇気流と下降気流」も深く関係しています(豆知識9)。
今回取り上げたジェット気流については、寒帯(ポーラー)ジェット気流と亜熱帯ジェット気流に大別されます。二つのジェット気流は、それぞれ寒帯および亜熱帯で、蛇行しながら地球を取り巻くように吹いています(ほぼ地球を一周する)。このような上空の強い西風の蛇行については、豆知識8をご覧いただけると幸いです。
今回の豆知識で参考にした図書等
●浅井冨雄(1998) ローカル気象学(第2版),東京大学出版会
●浅井冨雄,内田英治,河村 武 監修(1999)増補 気象の事典,平凡社
●安斎政雄(1998) 新・天気予報の手引(改訂29版),日本気象協会
●岩槻秀明(2017) 気象学のキホンがよ~くわかる本(第3版),秀和システム
●小倉義光(1999) 一般気象学(第2版),東京大学出版会
●気象庁のwebサイト
●気象業務支援センターのwebサイト
●中島俊夫(2022)イラスト図解 よくわかる気象学 実技編,ナツメ社
●新田 尚,立平良三(2004) 改訂版 最新 天気予報の技術,東京堂出版
●二宮洸三(2014)気象観測史的に見た高層気象台におけるジェット気流の発見,天気61:865-870
●福地 章(1999)高層気象とFAXの知識(第7版),成山堂書店
●福地 章(2023)よくわかる高層気象の知識(2訂版),成山堂書店